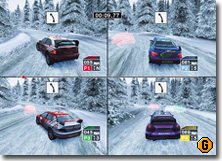Kanon(DC)
筆者 ヨッシーさん
まず最初にお断りしますが、これは自分が思うこと思うがままに書いたものです。
これを読んで意見反論あると思いますがご了承ください
このDC版KanonはPC版Kanon全年齢対象をDC用に改良して発売されたものである。
PC版は発売されてもうすぐ2年が経とうとしているが未だに販売本数を増やしている。
個性豊かなヒロイン達、そのヒロイン達に勝るとも劣らない個性豊かなサブキャラクター達(あまりこの言い方は好きではないが)が進めていくストーリーはほとんどのプレイした人達を「泣かせる」はずである
(中には泣かなかったという人もいるが・・)
しかし、Kanonは18才未満購入禁止のソフトであり幅広い年齢層にプレイしてもらいたいということで18禁の場面を削除し、削除した枚数分のCGを追加したのが全年齢対象版である。
DC版を発売するにあたって改良された点は、主人公を除くすべてのキャラクターに声が付いたことが挙げられると思う。
声優陣も有名どころを使っており、初めてプレイする人にはすんなりと受け入れられると思う・・・
しかし、PC版をしてきた人たちには???という部分もあると思うが、これは後述させてもらうと思う。
まず、このKanonの流れとしては、とある街に7年ぶりに帰ってきた主人公。
7年前の記憶はあまり確かではないがヒロイン達と再会と出会うことによって少しづつ取り戻していく・・・
その7年前の記憶と現在とが一つに繋がる時、物語は一気に進んでいく・・・
これは自分の思ったことだが
このKanonのストーリーに隠されているのは
「奇跡」と「越えていく強さ」
だと思っている。
例えばそれが最愛の人を失ってしまうかも知れないとか、今度くる誕生日を迎えることができないと、医者に宣告されていようが、彼女達は主人公と出会い、再会することで目の前に置かれた挫折してしまいそうな現実にも立ち向かっていくことができるのだと思う。
そのつらく厳しい現実にも立ち向かっていく強さを覚えた時に彼女達に訪れる小さな奇跡・・・
その解釈の仕方はプレイされた人達千差万別であろうからここでは特に書かないでおこうと思う。
後述させてもらうといった声についてだが、
はっきり言わせてもらえれば
「多少の違和感を感じている人達は余りにも自分で各キャ
ラのイメージを膨らませすぎているのではないか?」
と、思っている。
残念なことだが、そのイメージを余りにも膨らませしすぎた一部の人間が制作元であるKeyのHPの掲示板で心無い発言のため300件に及ぶ発言の削除、最後にはDC版Kanon掲示板の削除といった非常に残念な結果に繋がってしまった。
とはいっても、Kanonそのもののクオリティーは高いものがあるし、シナリオ・サウンドの面においてもPC版を経験していなくても十分に楽しめるものだと思っている。
5人(+1人)が織りなす雪降る街での小さな奇跡の物語は、現在の人間が忘れかけてしまっているものを思い出させてくれるような気がするし、物語後半では目頭が熱くなってくると思う。
最後になるがこのKanon購入しても損はないと無いと思う。
確かにギャルゲーだと言われてしまえばそれまでかも知れないが、既存のギャルゲーとは一線を画すソフトであるし「泣ける」ソフトというのはそう簡単にあるものではないと考えてる。
彼女達の持つ優しさ・強さそしてその彼女達に舞い降りる小さな奇跡の意味をプレイした後に考えて欲しいと思う。
「小さな奇跡はKanonをはじめた時からあなたのすぐ近くにあるはずです。
それは最初見えなくても後からきっと見えるはずです。
心に感動と一緒にやってきますよ」
ヨッシーさんのあとがき〜(笑)
最後のは凄く自分でもクサイ文章だと思ってます
でも載せるの?(かな)
なんか書いてて恥ずかしくなってきたし・・・
自分で書きますといっておいて二ヶ月近くも放っておいて大変申し訳ないと思ってます
メールアドレス公開しても構いませんので意見反論はこちらの方に回すようにして下さいませ
では 宜しくお願いします
「朝〜、朝だよ〜 朝ご飯食べて学校行くよ〜」
「夜は、おやすみなさい だよっ」
ねっ!! ノンちゃん(にははっ)
メアド”後悔”しちゃいますよ。(笑)ファンレター募集(笑)
良く書けたレビューで関心しました〜。すばらしい!約束から2ヶ月。待った甲斐がありました〜。
思うがままに>>
いえいえ。語ってなんぼでしょ。
オチも綺麗で好きですよ。
戻る
ガングリフォン(SS)
筆者 NONTAN
戻る
ガングリフォン・ブレイズ(PS2)
筆者 NONTAN
今回のお勧めの逸品はこれ!
「ガングリフォン・ブレイズ」
セガサターンの名作ガングリフォンシリーズの第3作目です。
(というか…今になって遊んでるだけで…みなさんからしたら懐かしいゲームですね…。自分その続編アライド・ストライクまで辿りついていませんし。。)
3でないのは…PS2に移植するにあたってのことなんでしょうかね。
ゲームアーツってセガ信者からは崇拝されてるメーカーですから、そのへんシビアに考えないとややこしそうですから。
で、ゲーム内容なんですが
いやぁ〜〜〜〜〜〜〜〜
ガングリフォンらしく難面白い(むずおもしろい)です。
なんていうんですか、敵味方の砲弾が入り乱れ、自分はまさに動く標的。
もっと激しく〜〜ってなマゾ的ゲームなこと皆さんしってましたか?
で、こっちもとにかく撃つ撃つ撃つ!!
これがたまらなく快感。SとM両方楽しいんですね(笑)
そういえばガングリフォンシリーズって、2から弾が見やすくなりましたが、これってまぁ賛否両論ありましたね。現実味に欠けてしまうと。
1のときは本当に黒い小さなものが飛んできましたし、撃たれたら当たってた。むしろガンガンキンキンドンドンよく見えない砲弾で常に撃たれている。
そんな男のゲームだったような。
でもですよ、ブレイズも敵の砲弾はすごく見やすいんです。
けど、逆にそれが砲弾の雨霰ってな緊迫した状況をすごく再現しているってことに気がついたんですよ。
でも、なぜに今更?2から砲弾は見やすかったじゃないってなあなた。
2の弾丸は細長い5角形でちょっと陳腐なイメージがあったんですよ。
ヘリからマシンガン撃たれてる様子なんか、小便小僧が小便を狙ってかけてきている〜〜・・・ってな光景に近いものがありましたでしょ。
でもPS2という媒体を得て、やっと砲弾も砲弾らしさが再現できて、こういった緊迫した雰囲気をかもし出せるようになったんですよね。
ただ、見えるようになったから避けられるかといったら別です。
ガンガンドカドカキンキン当たります。
そんな砲弾の雨霰の中、ガンガンキンキンドンドン撃たれながらも数々の戦場を戦う兵器なのですが…
自分が搭乗するのは16式装甲歩行戦闘車、通称HI−MAX3という兵器です。
あ…リアルな世界にはタブーな歩行兵器を…そう思いましたね。
たしかにちょっとアウトなんですけどね。。。
2足歩行なんて出してくると、階段で転んで起き上がれず足をバタバタさせるASHIMO君を想像してしまいますから。
しかも搭乗機のハイマックス3、かっこよすぎてこれまたいかんのですよ。
まさにこれじゃロボットじゃないですか。
でも、これはPS2に続編を出すにあたって狙ってきた部分ではあると思うんです。これまでセガサータンで登場させてきたハイマックスシリーズはあまりかっこよくなかったからですね。
かなりのおデブちゃん、かっこ悪すぎるハイマックス2。
避弾経始命!初代ハイマックス
あ、被弾経始というのは戦車の装甲を思い浮かべてもらうとわかりやすいんです。
戦車の装甲の前部って砲台にも車体にも装甲に傾斜がつけられているでしょ。
あれは飛んできた弾を逸らす効果があるんです。それを被弾経始っていうんです。
話は逸れましたが、どうですかこの無機質で無駄のないディテール。
「見える」ピキーーンってな感じでビームまで避けてしまうガ●ダムとは全然違うんです。もう鉄の塊。いかにも鈍重そうな兵器です。
そう…鈍重…だからガンガンキンキンドンドン撃たれるんですね。
動力だって間違っても核融合炉なんてものは出てきませんよ。
ガスタービンエンジンです。
なんてことはありません。ジェットヘリのエンジンですよ。
これで発電して手足を動かし、ジェットの推力でローラーダッシュ(ガスタービン+タイヤ)と短時間の飛行(ジャンプ)をするんです。
うむぅ…燃費は最悪でしょうね。実際ガスタービンエンジンの戦車なんてものもありますが燃費の問題から普及してませんから。。
ただ設定はあくまで2016年という近未来ですからね。
これくらいのほうがリアリティがあるんです。
ちなみにドイツのレオパルド2や日本の陸上自衛隊に配備されている90(きゅーまる!)式なんてものも戦場を駆け巡ってますよ。ブリキ缶なんていわれながらも…。
現在ですら片落ち感否めないこれら戦車って…
小学生の自分が学校の読書の時間に図書館で目をまるまるさせながら見ていた図鑑に載っていた当時最新鋭戦車達じゃありませんか…。
でもまぁあと10年ですよね。まだまだ現役張ってそうですね。
ゲームシステムの基本は当たり前ですがシリーズ通して一緒なんです。
歩行とダッシュとジャンプで戦場を駆け巡り、様々なミッションをこなしていくんです。やっている操作は3Dシューティングですね。
敵が出てきたら撃って破壊する。これが基本。
しかし戦場という立体的なフィールドというか箱庭を駆け巡る爽快感がこのシリーズの売りとなる部分。
進行作戦では配備されている敵の防衛ラインを突破もしくは武力制圧し、防衛作戦では次々と向かってくる敵を倒し拠点を守らなければならい。
中には拠点を放棄するといった作戦まである。
そうプレーヤーは戦場のヒーローではなく、ときには尻尾巻いて逃げないと駄目なんです。
どうだこのやるせなさ。敵の増援激しく、絶対太刀打ちできない面白さ。
けれども、それが戦場。
うん?自分が神がかり的にうまくなって敵を全滅させたらいいって?
広大なフィールドの四方八方から敵が出現してくるというのもありますし、それ以前にやはり弾が切れちゃうんですよ。
補給地点なんてものもありますがね。無限に補給できるわけじゃないんです。
取れば1回きりの補給アイテムが置いてあるんです。
だから実質弾は限られるっと。。
そうそう補給といえばこれまでのシリーズでは補給は補給ヘリでおこなっていましたよね。
補給ヘリ到着までに着陸地点を制圧して、補給を受ける。
補給ヘリがやられてしまってはクリアは絶望的。そんな男臭さがよかったんじゃないですか〜〜!
なのになんですか…戦場に転がるアイテムボックス。
無造作に箱がゴロゴロ置かれている場所が補給地点ですと!?!?
こんな火薬臭そうな男の戦場で誰が納得するんだ〜〜!!
それ以前に誰が置いたんだ〜〜!!これから進行していく場所にまで!
いくらPS2はライトユーザーが多いからといって、やってはいけないことをやってしまってますよ。
この1点だけでなんか台無し。
せっかく土煙と雨霰の弾丸と想像できる火薬の臭いで戦場をリアルに再現しているというのに…
この惜しささへなければ最高のゲームだったんだろうなぁ。。。
戻る
機動戦士ガンダム外伝 コローニーの落ちた地で(DC)
筆者 NONTAN
このゲームはファーストガンダムの世界を元にした、3Dアクションシューティングです。
ガンダム外伝はSS版で3部作として出ており、システムは前作の作りを踏襲した形になってはいるのですが、ストーリーはまったくのオリジナル作品になっています。
自分としては、前作はEXAMシステム(コンピューター補助によりニュータイプ並の反応ができるようになるシステム。反面、人の意志の集中する戦場等ではEXAMシステムがそれに反応し暴走してしまう危険性もある。)というアニメアニメした設定に嫌気を覚えながらもブルーディスティニー(主人公の搭乗するEXAMを登載した機体)の化け物じみた運動性などの迫力に圧倒され、いつのまにかブルーの魅力に惹かれていました。
そのためか今作はブルーのようなオリジナルMSの登場がないと知ったとき、どことなく地味な印象を受けてしまいました。
しかし、プレイしてみたときそこにあったのは紛れもなく戦場だったのです。ミノフスキー粒子によるレダーの無効化によって、たよるものは己の視覚と聴覚そして勘。
まさにこれがこのゲームの醍醐味になっています。レーダー有効範囲はあまりにも狭く、敵からの砲撃音により敵のいる方角を察知し、視覚で捕らえ反撃に転じるといった戦い方がメインになり常に戦場の緊張感が付きまといます。
敵を発見しても、1対1では倒すころにはこちらも消耗してしまうので、味方に指示を出して3対1で格個撃破など「いかにこちらが有利な状況を作れるか」などの戦術性も存在しいて、これにより小隊長の気分が味わえるようになっています。
もちろんDCのグラフィックレベルの恩恵も受けグラフィックの進化も凄いです。
最近の映画などのCGレベルは凄いのですが、見慣れてしまうとそこに驚きを感じることはできません。
ゲームも同じで、どこか見慣れてしまうとどれも同じに見え新鮮味に欠けていたのですが、このガンダムのオープニングは明らかに今までのとはレベルが違います。見てみなければ解りにくいので余り触れませんが、一言でいうとMSの存在が何の違和感なく世界にマッチしています!。オープニングなんてオマケの一つと考えてる人たちもこれは見てもらいたいです。
そしてポリゴンのテクスチャーから見てとれる油、火薬臭さは私たちの知る範囲の戦場というものに違和感なく当てはまりロボットではない兵器としてのMSを表現することに成功しています。
オープニング、3Dポリゴン、配色、MS3機に指揮車両1台、キャラのセリフ。
つまりこのゲームが目指したものはミリタリーであるガンダムだったのではないでしょうか。
今まではどこか[ガンダムゲー]=[キャラゲー]=[作りが甘い、名前だけで売れる]=[クソゲー]というイメージがあるのですが、(これはガンダムと名のつくゲームなら買ってしまう自分のようなガンダムファンが原因ではあるのですが(汗))最近のガンダムゲーには当たりが多い!(ギレンの野望、Gジェネなど)ガンダムを知らないユーザーもこの機会にガンダムゲー触れてみてはいかがでしょうか?
徹底的に世界観、戦闘、設定、ミリタリーなガンダムらしさにこだわったこの作品にはガンダムを知らないユーザーにも「面白い!!」と言わせる内容を持ているはずです!
あとがき〜〜〜
今回ポリゴンのモデリング、敵の攻撃方法、登場のシチュエーション等ガンダムファンが感動する要素について触れなかったのは、ガンダムを知らない人にガンダムの内容をうだうだと説明したとこれで意味がない、逆にマニアの自己満足な世界と思い書きませんでした。しかしグフがヒートロッドで攻撃してきたり、アッザムがアッザムリーダー使ってきたときは感動したな〜〜モデリング、ステージ構成は文句無しだね!!
戻る
機動戦士Zガンダム前編(SS)
著者 NONTAN
いきなり年がバレるようなことを書いてしまうのだが、Zガンダムは私が小学校3年生当時にTV放映されており、幼稚園の頃再放送で見ていたファーストガンダムより思い出らしい思い出は多い。
この当時学校ではZガンダムのガチャポンが大ブームで、なけなしのおこづかいをはたいてはガチャポンを買い、欲しくも無いガザCやアッシマーを山のように当てていた記憶もあれば、プラモを買うにもお金がないので144分の1が欲しいと横目でみながら一番小さなサイズである300円のプラモを買っていたり、時には母のサイフからお金を盗んでプラモを買っていたのがバレてお尻がはれ上がるくらいまで叩かれたり、、、、、。
と、なんとも子供らしい子供をしていたもんだなと懐かしい記憶に浸れる。
しかし、この記憶からわかるように自分はガンダムのストーリーの記憶よりもオモチャ等の記憶しかいないのだ。
現在、自分がZを語るときに使われる知識(おおげさ・・)といえば19歳頃にでたZガンダムのビデオ(全13巻)であり、それを見てようやくZガンダムのストーリーを把握したのだ。
ある程度大人になって見たZガンダムは私にガンダムの面白さというものを再確認させた。
暗すぎると賛否の分かれるストーリー、玩具を意識したとしか思えないような変形機構を取り入れた第3世代MS。
色々な問題を抱えつつも年が年だけにある程度視点に距離を置くことが出来たことが、純粋に世界観、背景、ストーリーを楽しむことの要因となったのだろう。
っと、、このままではゲームのレビューではなくなってしまうので思い出話はここまでにしておくとして、横スクロールシューティングとして評判のよかった機動戦士ガンダム(SS)のシステムにマイナーチェンジを施し発売したこのゲーム、出来の悪さはかなりのものである。
一言で言うとゲームバランスが最悪である。前編というだけあり自機はガンダムマーク2のみ。それで最後まで戦うことになるのである。
これでメッサーラやサイコガンダム、ギャプランなどを相手にするのだから苦戦して当たり前と言われればそれまでなのだが、、、、、やられるたびにスキップできないセリフつきのカットインを見せられるとなればストレスをためるためにゲームをしているように思え、自分のア●さを自然に悟らせてくれるのである、、、。
ここでこのゲームをプレイしたことのある方なら誰もがあるシーンを思い出すであろう。
そう、、、2面のメッサーラ、マラサイ戦である。
画面の奥から手前からと攻撃してくるメッサーラは手のうちようが無い強敵。
こいつを倒すために全国で何個のコントローラーが破壊されてしまうのだろうと・・?といらぬ心配までしてしまうほどなのだが、撃破したところでライフゲージそのままに2体のマラサイと勝負となる・・・
しかもマラサイでやられてしまうとまたメッサーラからやり直しなのである・・・・
これをクリアすることはある意味ガンダムファンとしての頂点を極めるに等しいかと思えるのほどだ、、、、。
それは次第に怒りとなり目の前で開発者にプレイさせてみて「これが本当にゲームと呼べるものなのか」と問いただしたくもなる。
その後は空想に近い世界に入り「ニュータイプってやっぱりすごいんだ・・・自分がカミーユの変わりになれるわけないよね・・・」と空想の世界というゲーム本来の世界を少し皮肉って堪能するのである、、、、。
そして、前作と呼べる機動戦士ガンダム(SS)で新たに書き起こされたアニメーションムービーと同レベルのムービーを期待しつつも、最後までTV版そのままをキャプチャーしたムービーを見て「ビデオをそのまま見たら済む話だ、何故にゲームでしかもこんなにまでストレスをためながら、、、」と思いつつもZガンダムの世界を堪能するのである。。
何をどう理屈で固めても救いようのないほどつまらないこのゲームはガンダムというある意味宗教に近い世界から解脱するための一筋の光的存在なのかもしれない。
しかし、このゲームをクリアしてしまった人(自分もふくめ)はこのことがある意味誇りとなり、ますます墜ちていくための諸刃の剣なのかもしれない。
「人は何故同じ過ちを繰り返す・・・・まったく・・・・・・・・」
アムロも言っているようにいい加減ガンダムと名の付くゲームだという理由でガンダムゲーを買ってしまう自分は地球の引力に魂を引かれた人間の象徴なのである。。
こうしてまた自分はZガンダムのほろ苦い記憶を1つ増やし、刻(とき)の涙を見るのであった・・・
あとがき〜〜!!
このゲーム・・買うならネタとしてだけにしましょう・・・・・・・・以上
戻る
クォヴァディス2惑星強襲オヴァンレイ(SS)
筆者 NONTAN
このゲームは人それぞれの生き方をテーマにしたリアルタイムSRPGである。
大統領暗殺未遂を大義名分として惑星統一に乗り出した、セテウア星系一の経済力を持つ国家[GOA]と、それに反対し各惑星の急進派が集結した政権[八惑星連合]との戦争に翻弄され苦悩する主人公を中心にストーリーは進む。
ゲームのウリはなんといっても豪華なアニメスタッフではないだろうか。
キャラクターデザインに美樹本晴彦、メカデザインに藤田一巳、監督に板野一郎と豪華スタッフが揃っているのだ。
そのためミッションの間に挿入されるアニメーションの演出はうまく、アニメとCGの合成も非常に美しく鳥肌が立つほどかっこよく仕上がっている。
リアルロボットアニメ好きには正直これを見るためだけに買っても損はないはずだ。
(このゲームがビデオ化されて欲しいと願うのは自分だけではないはず?特に飛んでいくミサイルの軌道、戦艦からの 発射シーンは必見。まさに板野サーカス)
戦闘は一見地味でフロントミッションなどを好む人には見ただけでダメという人もいるだろう。
メカもの好きなゲームファンはその中にガンダムやボトムズを求める傾向が強く、このゲームのように小さい点のようなメカを上から見ているだけでメカ自身が何の動きも見せないまま弾丸やビームが飛び交うのでは満足できないからだ。 (格闘ではアームをバタバタさせるが、)
これに関しては対策のしようはあったはずだ。
メカにカーソルを合わせボタンを押すと時間が止まり3Dの戦闘シーンが見れるようにする、破壊シーンのリプレー表示をするなど自分でも色々な案はでる
しかし、やり慣れてくるとそういった点は気にならず、どういった戦術を取るか、どのユニットでどんな展開をしていけばいいかなどの要素に熱くなれる。
『適発見』『破損大なんとかしろ〜』など、味方から次々入る通信への対応に大忙しで、これが非常に場を盛り上げリアルタイムSRPGならではの心地よい緊張感を味わうことが出来るからだ。
そうなると逆に時間を止めるような要素はなくて正解だったようにも思える。
戦闘は
移動が早く格闘を得意とする[フェロン]
能力はどれも平均的な[モータル]
移動、索敵、射撃の得意な[スナイパー]
射撃、装甲が強い [ホボー]
の4種類のメカを駆使して闘うこととなる。
もちろんそれぞれのメカに合わせた装備ができるようになっている。
戦闘には包囲効果というシステムが戦術としてかなり重要で、敵を包囲することで敵の攻撃力、防御力を低下させることができる。
(索敵範囲に敵が入らないと敵は表示されない)
そのため移動、索敵の得意とするスナイパーで敵を探し、敵をスナイパーに向け反対からフェロンで近づき包囲効果を利用した格闘で撃破するなどいろいろ凝った戦闘が楽しるのだ。
戦闘終了後には戦闘時間、撃破数などでランク付けがされるのでやりこみ度が高いことにも関心できた。
(この辺りのバランスは逸品)
ストーリーも良くできている。
平和のための理想論など語ったりせず、主人公も正義ではない。
時には田舎の集落を戦場とし、罪のない人々を戦争に巻き込んでしまうこともある。
戦争ものとしてはよく仕上っているのではないのだろうか。
キャッチフレーズの「勝利のために 君は何を失うのか」この通り主人公の怒り、苦悩、絶望にこだわったシリアスに展開されるストーリーはエンディングでプレーヤーの涙を誘うであろう。
この、クォヴァディスシリーズは 3部作の予定だったのだが残念なことに開発元のグラムスは倒産してしまい、まことに残念ながら続編はでなくなってしまった。
今日のゲーム氷河期には、こういった 中小メーカーには辛く、広告を大量に出せる一部のメーカーだけが売れるのは仕方が無いと言えば仕方が無いのだが、よい作品であるため残念でならない。
あとがき〜〜〜
今回もイベントに関しては何も書きませんでした
正直このゲームは賛否両論ですが、世界観、ストーリーはいいので触れてみて損はないはず!!
戻る
グランディア(SS)
筆者 NONTAN
グランディアとは冒険、友情、出会い、そして別れをテーマにしたストーリー重視のRPGである。そしてその中身は制作者のこだわりが見られる、すばらしい作品に仕上がっている。
まずゲームアーツのRPGには大抵言えるのだが、町の人とのセリフのやりとりが面白い。
大抵のRPGには必要最低限のセリフしか用意されてなく、同じことを何回も話し、必要な情報を集めるにもストレスがたまる場合がある。つまり町の人がヒントの掲示板でしかないのだ。
しかしグランディアは町の人のセリフパターンが多い。
(ジャスティン(主人公)が話しかける→町の人が答える→ジャスティンがぼける→スー(主人公のおさな馴染み)のツッコミ)など。
ジャスティンのリアクション、スーのツッコミなどは見いるだけで微笑ましく楽しい上、パームの町の中でのジャスティンの行動が想像でき、冒頭からすんなり物語に入れるようになっている。
そして小さく横に表示されるウィンドーの顔の表情はパターン数も豊富で、さらに会話のシーンを盛り上げる要因となっている。
イベント後などに変わるセリフのパターンも多く、町の人一人に付き最低5〜6パターンのセリフがあるのには驚いた。
これによりこのRPGにはヒントの掲示板ではなく町の人一人一人がその町で生活してる錯覚に襲われるのだ。そして自分はRPGにおけるセリフの大切さを改めて教えられた。
ポリゴンで作られた町も非常に美しく、一つ一つの町に特徴があり、ここにもゲームアーツの妥協を許さないこだわりを感じる。
ギミックのパターンも多く、壁に掛けてある斧が落ちたり、樽が揺れたり、つい色々試したくなる。
流れる川も美しく、近づくにつれ水の音が大きくなったりもするので、新しい町を探索する楽しさを久しぶりに味わえたゲームでもあった。
戦闘もこのゲームの売りの一つであり、非常に戦術性がある。システムを言葉で説明すると長くなりすぎるので省くが、相手の攻撃モーション中に攻撃するとカウンターを当てたり、キャンセルさせたりすることが可能で、相手の先手を取ることにより戦闘の流れを自分のものにできたりもする。
逆に後手に回ると相手のペースにはまり、最悪攻撃することもできないような事にもなる。これが特にボス戦では楽しく、その戦闘の流れの取り合いになりかなり白熱する作りになっている。
ゲーム音楽もこのゲームを盛り上げる要素の1つになっており、場面場面に合わせた音楽センスは非常にすばらしい。
これは今までゲームアーツのゲーム音楽には馴染みの深い岩垂さんの音楽センスでもある。
SEも凝っており、振れるとカサカサなる葉っぱ、近づくとパチパチなている焚火など映像と合わせると、その空間が存在する錯覚に襲われることまちがいなしと、細かいことを揚げるときりが無いほどだ。
そしてなにより、このゲームはストーリーがだらだら流れ、綺麗な映像だけを売りにするような昨今のRPGとは違い、どこを取っても開発者の妥協を許さないゲームに対するこだわり、想いをジャスティンの冒険という形を取って現したのではないだろうか?
(冒険心を忘れない純粋な少年、すなわちゲームアーツ、冒険を手軽なビジネスにしてしまった冒険者協会、すなわち昨今のRPG)
昨今のネームバリューで売れるゲーム、広告だけで売れてしまうゲーム、そういったゲームに従来のやり方で勝負を挑んだこのゲームは自分にとってゲームの在り方を考えさせ、ゲーム離れしていく自分にゲームの楽しさを再認識させ、ゲームアーツの開発者に感謝すらしたくなった。
このゲームを皆さんにプレーして頂きゲームの在り方をもう一度考えて頂きたい。RPGの本質これがこのゲームの全てではないだろうか!
あとがき〜〜〜
イベントに対する思いは沢山あるが、ネタばれ危険のため、今回はストーリーに関する事は排除しました。 しかしストーリーは涙することまちがいなし!! 息子の旅立ちを前にする母の心境など(従来のRPGでは、がんばて世界を救えよ〜くらいなもんなのに。)ううう、かきた〜い
グランディア(SS)
筆者 鈴木その子 さん
グランディアはスルメゲー
まず最初に驚いたのは町の人との豊富な会話パターン。
一人につき、ほぼ必ず3回話しかけないと、全パターン見ることのできない。しかもほんの少しストーリーに進展があっただけでまた町の人の言うことが変化する。
勿論またまた三回ぐらい話しかけなくてはいけない。さらに
だいぶ話が進んでから以前立ち寄った町に戻ると、またまた
違う反応が返ってくる。冒険者協会の会長が(自主規制)してたとかね。 そんなこんなで会話して回るだけでめちゃめちゃ時間がかかる。でもこれがまた楽しい。
さらに、笑いあり、泣きありのストーリー。
ネタバレはまずいんで詳しくは書けないけど、俺が一番印象
に残っているのは(自主規制)と(自主規制)れる所かな。
泣けるとこやね。(なんのこっちゃわからんか!?) 友達
に貸したら、このシーンで泣いたそうですわ。
曰く、「ゲームで初めて泣いた」んだそうだ。わかる、わかる。多分このゲーム中一番の名シーンでしょう。
とにかくこのゲーム、急いでやっては損ですぞ。時間をかけてどっぷりと世界に浸るのが、正しい遊びかたでしょう。(強引な締め)
のんたんの感想〜〜!!「グランディアはスルメゲー」というタイトル付のレビュー素敵です。時間を掛けてじっくりやるとますます味がでる。正にその通りだと思います。ネタバレを極力抑えた伏せ字にはおもわすニヤリ。
戻る
グランディア デジタルミュージアム(SS)
筆者 鈴木その子 さん
ファンディスクと言えばグランディア
グランディア デジタルミュージアムって奴なんだけど、あれはよかったな〜〜
よくあるファンディスクって乱暴な言い方をすれば単なる資料集みたいな感じになってるけど、これは違ったね。(ま、だから買ったんだけど。)
勿論資料集的な役割もあるけど、これだけでも一本のゲームソフトとして成り立ってると言ってもいいぐらい、内容がつまってた。
まずなんといっても当然なくちゃいけない豊富な資料の数々
。設定画面やら、ラフデザイン画やらとにかく沢山入っていて、ファンならウハウハでしょう
そして新録のダンジョン。本編の使い回しではなく、全く新規のダンジョンで、しかも本編より難易度が高くなっているので、やりごたえ抜群
そして個人的に一番楽しんだのが、これまた豊富なミニゲーム。いろいろある中で俺が1番燃えたのが野球ゲーム(男の
熱血100億番勝負)要はホームラン競争みたいなもんだけど投手のラップ君が投げる球ってのが正に魔球で、トンでもない剛速球に、消える球、打者の前で一回転する球などめっちゃくちゃ。 しかし、これを100本中50本ホームランにすれば貴重なアイテムがもらえるとあってはやらずにはおれん!そして練習しまくって、見事達成したのでした。
とにかく燃えるで〜〜ミニゲームは!
そんなこんなで盛りだくさんのこのゲームファンならやらずには死ねんぞ〜〜!!
その子さんのレビューの締めは個人的に大好きです。このレビューにより何を伝えたかったかがよく現れてますね。「死ねんぞ〜!」「ウハウハ」などの言葉使いも大好きです。その子さんらしい味が出ています。(知ってた〜?自分その子のレビューのファンなんだよ。)
戻る
グランディア2(DC)
筆者 NONTAN@P
次世代RPG。これはグランディア2のキャッチコピーである。
PS2、DC、後にはドルフィンなどを控えた今、ハードの表現能力は格段に進化を遂げている。そしてRPGはいつしかグラフィク、ストーリー重視へと進化を遂げてきた。はたして今作のグランディア2が目指した次世代RPGとは何であったのだろうか?
ハードはSSからDCへと変わり、グラフィックは格段に進化している。
しかし、単に美しい映像だけを目指した訳ではなく、造形美そのものがすばらしい。リアルな建物は少なめにして、曲線を多用した独特な町並。
そこに住む人々の様々なセリフ、そこへ雰囲気の合った音楽を入れる。
この要素が揃ったとき、グランディア独自の世界観が生まれる。そして、そこにはグランディアを象徴するかのような暖かな空気すら感じとれるのだ。
しかし、グラフィック進化の弊害もあることは事実だ。
前作からの問題点であった魔法エフェクトの長さ。
迫力の映像を表現してはいるのだが・・、これではボス戦などが意味もなく時間のかかるものになってしまう。
続編なだけに何の対策も練られていなかったのには疑問を感じてしまう・・。
だが続編として、良いところも数々受け継がれて、さらなる進化を遂げている。
マップ配置型の敵キャラは前作と同じシステムを継承しているのだが、今作ではマップを広めにとり、敵を避けやすくする配慮がされている。
成長システムも前作では使用した武器、魔法のみが成長するシステムであったが、今作はポイントの振り分けによるレベルアップ方式へと変更されている。成長の片寄りを防ぎ、自由なキャラを育て上げる。これはライトユーザーを意識したシステムだと言えるだろう。
そして、グランディアがRPGというジャンルの中で秀でた要素の、テキストの多さ、音楽の使い分け。
音楽とは記憶を蘇らせるものである。透明感のある神秘的な歌はシーンを音楽そのものが引っ張るという作りになっており、プレイヤーへの記憶の植え付けをしているのだ。
そして、ドラマを見せるという形式が確立されつつある作今の客観視点型RPGの中で、プレイヤーの感情移入の要素は、そのRPGを左右する最大のポイントである。
その点、グランディア2は町の人のセリフ(テキスト)の多さがその点を解決している。
セリフはストーリーを理解させるためだけのものではなく、ヒントの掲示板でもなく、プレイヤー自らが受取に行くことにより、何気ない会話を通じて物語の中へ入ることができるようになっているからである。
自らの行動が感情移入へと繋がる。これこそがグランディアなのである。
以上の点により、今作は冒険というテーマではなかったにしろ、そこで私が感じたものは、まぎれもなくグランディアそのものであったのだ。
つまり、グランディアが目指した次世代RPGとは、原点回帰による、ドラマではなくゲームとしてのRPGだったのではないだろうか。
幼いころ登った木。足を滑らせ何回も落ち、それでも上に辿りつきたいの一心で登った。辿りついたとき、そこに広がる世界の広さの感動は今でも忘れない。大人になって再び登り、幼い頃見た世界はそこになかったとしても、幼い頃の感動は蘇ってくる。
RPGといジャンルこそ、幼い頃登った木そのものではないだろうか?
いつしか私はRPGにお手軽なハシゴを求めていたのである。
しかし、そこには幼かった頃に見た世界は存在していなかったのである・・・。
グランディア2のエンディングの感動に浸り、レビューを書いてる今、各場面の記憶が走馬灯のように蘇ってくる。
しかし、グランディア2が幼い頃登った木になるかはまだ解らない、、、。
でもグランディアという木は私の心の中に根付いたものだと私は信じたい。
あとがき〜〜〜〜!
RPGをめんどくさいと考える自分が何かに取り付かれたように6日でクリアに至ったのは、そこにグランディア1という木があったからだと思うね。本当に今作は良い意味で裏切られました。テーマは違うものの、中身はグランディアそのものだったから。RPGレビューはどうしても主観で語りがちになるけど、自分はこういうのが好き。ちなみに一番大きな木は天外魔境2。やっぱ思いでは美化されてる?
戻る
クレイジータクシー(DC)
筆者 NONTAN
以前、従姉妹(80年生まれ)の家にDC本体とクレイジータクシー(以後クレタク)を持っていったときのこと
「あ〜これTVでやってた。タクシーのゲームでしょ?(そのままやん・・・)面白いらしいね〜。」と、普段DCのゲームなど見向きもしない、ゲームと言えばプレステと思っている女の子がクレタクに反応してきたのだ。
たぶんテレビではもっと沢山のゲームが紹介されてるであろうが、クレタクの見た目のインパクトの強さで印象に残っていたためであろう・・。
自分はそのコメントに対して、
「このバカさがやってておもろいで〜。」と、バカの一言で表現したのだが、実はバカゲーという言葉でクレタクを表現したくはなかったのだ。
しかし相手があまりゲームを知らないために、相手に合わせた表現がバカの一言だったのである。
真のところ、自分の思うクレタクとは、「賢いからこそバカを知りつくし、バカを演じることの出来るインテリゲー」なのである。
クレタクの醍醐味は、対向車線であろうが、公園の中であろうが、ビルの屋上であろうが何の関係もなくあらゆるところを走り、電話ボックスを跳ね飛ばし、跳ね橋をジャンプ台に大ジャンプするなど、現実では不可能な大暴走をすることの爽快感にある。
しかし、単なるバカでは、ここまで爽快感を得ることは出来ないのではないだろうか?
街の作り一つにしても、ショートカットポイント、ドリフトポイント、目的地での理想的な止まり方など、遊べば遊ぶほどに新たな発見があり、破壊出来るオブジェ、出来ないオブジェの存在意義までもが、きっちりと計算されて作られていることに気がつく。
しかし計算されているのはあくまでも遊びの範囲を狭めるためにあるのではなく、コンボの稼ぎ方を自分で探すスコアアタックのために用意されているのだ。
そこに、ど派手な火花、コーナーでの車体の傾き方、ノリのいいサンドなどを融合させ、その爽快感を一層盛り上げている計算されつくしたゲームなのである。
そのことから先に述べたようにクレタクとはバカであるとは何かを計算尽くしてバカを演じた”インテリゲー”だと自分は考えるのである。
洋ゲーには斬新な発想を取り入れたバカゲーが多いが、頭のいいバカほど奥の深いバカは存在しないだろう。
近年ハードの進化に伴いリアルな表現をされたゲームが増えたことから、リアル思考のゲームが増えた。
しかしゲームらしい発想を持ったこのゲームにどこか懐かしさを感じながらも、「ゲームはゲーム。その思考はまだまだいける!」と心の中で叫んでいる自分を見た。
あとがき〜〜〜〜!!
バカゲーの批評もやっぱバカなくせにうんちくを述べる自分より、計算してバカを演じることの出来る、鈴木その子が書いた方が面白かっただろうね(^^;その子にクレタクレビュー頼もうかな〜〜・・。
戻る
コリンマクレー・ザ・ラリー2
筆者:555)))
日本で唯一のラリーゲームメーカーのスパイクから発売されました『コリンマクレーザラリー2』略〜cmr2、前作とは全く比べ物になりません
画像、音、車種、どれを取っても悪いとこありません
車やコースの大きさなんかはビデオを見ている感じです
ssも実際のコースを再現しているので凄くリアルです、砂煙やバックファイヤー等も再現されています
しかし、やはり不満もあります、まず「アーケード」これは全く無意味で必要ないです
やっても敵車はセコイし速いし勝っても何もありません
どうでも良い車が2台もらえます
それは、ランサーエボしかも色が少し違うだけのゴミ車です、あと、開催国も少ないなぁ
8ヶ国しかなくて一ヶ国ごとにsssがあるんですけど、
やはり制作している時期に行われている開催国を入れてほしかったなぁ、それでssは1〜10まであって、sssは1ヶ国ごとでss11になります
コースの長さは速く走っても3分程度です
凄いと思ったのは「チャンピオンシップ」で
天候がランダムで替わり、走ってる間も変わる時があるんです、「シングルラリー」では自分で設定出来ます
車種によって、動きが全く違っていて、セッティングも車種によって全て替えなくては同じコースでも走り方が変わってきます
ドライバー視点でコックピットのドライバーの気分が味わえます、車種によってコックピットの中が違います
ラリーに欠かせないコ、ドライバー(ナビ)は実際マクレーのコドライバー、グリストの生声です
とにかく種類が多くて、実際もこういう風にやってるんだなぁ〜、て感じです
それと、マシンはぶつけたりすると当然壊れていきます
エンジンやブレーキ、ハンドル等、ボディやガラス、エアロまで損傷して、ひどくなると、外れていきしまいには動かなくなります、試しにどこまで壊れていくかやってみました
スピード感はですね、コースの幅や大きさ、マシンの大きさもあるけど、V−RALLY2より落ちた感じですけど、GT2やSR2よりはスピード感あるようです、視点によっても違うようです
なんか、まだあっような・・・
とにかく、買ってみてやってください
ちなみに僕はPS2でプレイしてます
来年にPS2でWRCゲーム発売するようです
のんたんの感想〜
またまたWRCのゲームのレビューですね。
いやぁ〜WRCものを読むたびに欲しくなってしまいます。マシンが汚れて壊れながら走るのもラリーの醍醐味です。マクレーラリー1にはマシンが小さい、荒い、汚れが不自然という欠点はありましたが2では解消されてるようですね。
久々にWRCが題材のゲームがやりたくなるようなレビューありがとうございました。
戻る
コリンマクレーラリー04日本語版(PC)
筆者:555さん
実に久しぶりのレビューです「コリンマクレーラリー04」PC版です
なんといってもメインであろうオンライン対戦です
対戦相手はゴーストカーのように赤い影のように表示されていて、あまり相手と対戦しているという実感がなく、COMを相手しているようで少し残念な感じです。
が、しかしやはりオンライン対戦ははまります面白い、相手国もさまざまですがほとんどヨーロッパの人のようでいままで日本人と対戦したことないです(−Q−)
韓国か中国の人は何回か相手したことがありますが(−Q−;
画像はいままでPS2でやっていたWRCとは比べ物にならないくらい綺麗で細かいとこまで作りこんでいます、いうにおよばず、ということです、そしてそしてこの作品には日本ラリーがあるというとこです
ここのコースは実際ジャパンラリーのコースとは違うとこで峠のターマックで全て雨のコースです、視察しにきた時の時期が悪かったのか嵐になっていて難易度も高いです
でも実際北海道の人なら誰でも知っている本当にある峠でなんだかうれしいです、町並みや看板、ドライブインも手をぬくことなく作られていました観客も日本人でした
車種もランチアデルタやアウディなど懐かしいボーナスカーもあり某WRCシリーズのようにクリアーしたらすること無し、結果売るということもなく長く遊べる作品です
巻き上がる煙、雪、水、全てにおいて最高に優れているともいます
モアモア〜〜〜〜と消えていくとこが良い(^Q‘v
欠点はコース、開催国が少ないとこでしょうかSS8+SSSは少ない感じがします、オンラインで対戦相手がゴーストというのもなんとなく残念です
しかししかし、発売から1ヶ月でなんとまたまた「コリンマクレーラリー05」発売されましたな、日本語版はまだのようですがオンライン対戦はないようです、まだ早いだろ〜といいたいですが、、、
コリンマクレーラリー04追加記事
大事?なこと書くの忘れてました、当然のことかもしれませんがクラッシュするとマシン壊れていきます、ボディも粉々ボンネットやドアも走っている時にはずれたりタイヤが転がってスピンしたり、最終的にはどうなるのか試してみましたが、オイル漏れしてエンジンストップしました
チャンピオンシップモードではリタイヤになります
オンライン対戦でも同じです
四輪タイヤなしでホイールのみで走ることも可能ですがそのうちホイールもはずれてデスクだけになります
それはそれで面白いかも
フィンランドの湖や川に沈めることもできます、上がったら煙がでます、でも故障します、川は走ることもできますがしばらくしたら戻されます、これは面白い
オンラインではだれがどの国の人なのかプロフィールみたいなのがあるのですぐ解ります、チャットもできますが英語やヨーロッパの言葉は解らないのでチャットはいまだにしたことがないです、顔文字のみ、、、、(;Q;)
環境音は自分の持っているスピーカーへぼいので省略します、スピーカーは推奨環境ではないので、、、
コ、ドライバーはマクレーのシトロエン時代の方がしゃべっていますが個人的にはニッキーのほうが好かったです

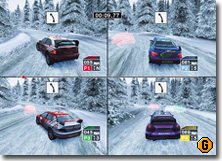


NONTANの感想
いやぁ…綺麗です…。GT4の開発画像を見て「これ以上すごいものは見たことが無い」なんて言ってたのですが軽く越えちゃってますね。
X−BOXがPCを越えたなど言われていますが、これを見るとPCもまだまだ・・・。いやぁ凄いです。
しかし外国人ばかりのオンライン対戦は少し寂しいですね。
モータースポーツがあまり盛んではない日本では仕方の無いことなのでしょうか…?
かといって盛んになると峠は走り屋さんだらけになるのかな日本では…?
そうなるとヨーロッパの峠ってどんなでしょう・・・変なところが気になりますね・・・
戻る
戻るの??
|